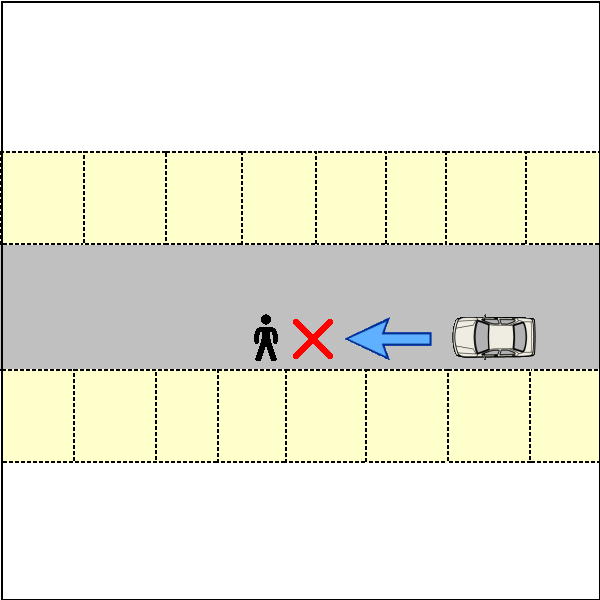交通事故で怪我をした場合、治療費の問題や過失割合の問題、相手からの示談案の妥当性、保険会社との交渉によるストレスなど様々な課題が起きますが、交通事故に何度も遭うこと自体まれなことであり、多くの方にとっては一生に一度のことです。
そのため、人身事故の被害者が相手の保険会社の言い分が正しいのかどうかを判断することは難しく、適切なタイミングで弁護士が関与することによって迷う場面を少なくすることができ、また、最終的に妥当な内容で解決できることも期待できます。
もっとも、いざ弁護士に相談しようと思っても、どのタイミングで相談すれば良いか自体わからない方も多くいらっしゃると思いますので、今回はこの点をテーマにお話ししたいと思います。
人身事故で弁護士に相談するタイミング
1 事故直後
事故直後は、警察や保険会社への連絡といった形式的な手続きをすることで手一杯であることが多く、そもそも怪我をしている場合はまずは治療に専念することが最優先ですから、弁護士への相談が後回しになるのも仕方がないといえます。
もっとも、怪我の治療の受け方によっては、示談交渉や最終的な賠償額に影響する可能性があるため、可能であるなら、ご本人でなくとも弁護士に相談した方が良いと思います。
特に、骨折等を伴わないむち打ちのケースだと、通院先が適切かどうか、通院頻度はどの程度が適当か、将来的に受けておくことが望ましい検査など、後の後遺障害等級認定や示談交渉を見据えてあらかじめ見通しをつけておくことが有効な場合がありますので、相談に行くことを検討していただきたいと思います。
2 治療継続中
この段階では弁護士への相談の優先度はそこまで高くはありませんが、ある程度治療が進んだ時点では相談に行った方が良い場合があります。
治療継続中は相手方の保険会社が治療費を内払いしているケースが多いと思いますが、事故からある程度の期間が経過すると、保険会社から医師への医療照会によって、治療費の支払いを終了すると通告される可能性が出てきます。
医師の判断と自分自身の感じる怪我の治り具合が一致していれば問題はありませんが、もしもまだ治っていないと感じ、治療費の内払いも継続してもらいたいという場合には、今後も治療によって症状が改善する可能性があることを診断書などで示してもらい治療費の内払いの継続を保険会社と交渉する余地もあることから、そのような場合は弁護士へ相談に行った方が良いと思います。
3 完治、あるいは症状固定
交通事故による怪我が完治した場合にはその時点で事故による損害はすべて確定したことになりますので、今後の進め方を確認するためにも弁護士に相談するタイミングとしては良い頃合いです。
また、治療を尽くしたものの治りきらず、これ以上続けても治療効果があがらないと医師が判断した場合(症状固定)にも事故による損害が確定したことになるため、やはり弁護士に相談するタイミングということになります。
後遺障害が残った場合には、その残存症状が自賠法所定の後遺障害等級(1~14級)として認定されるかどうか、あるいはその等級が何級になるかによって最終的な賠償額に大きな違いが出てきます。
もっとも、ご相談を受けていると、すでに作成された後遺障害診断書において、相談者の訴える自覚症状が適切に記載されていなかったり、自覚症状は記載されているものの、その症状の裏付けとなる医学的検査が実施されていないか乏しい場合もあります。
後遺障害等級認定は書面審査であるため、適切な認定を受けるには後遺障害診断書に必要な情報がきちんと記載されていることが必要ですし、一度作成してもらった後で書き直しや検査の追加を依頼するというのは気が引けて難しいこともあるかと思いますので、後遺障害があるときは、できれば後遺障害診断書を作成する前に弁護士のアドバイスを受けることをお勧めします。
4 保険会社からの示談案が出た時点、あるいは本人による交渉が決裂した場合
この段階では、怪我が完治したり認定された後遺障害等級に問題がなければ最終的な金額の妥当性のみが問題となっていますので、弁護士へ相談に行くタイミングとしては適切です。
このタイミングで相談を受けた弁護士は、聞き取った事故状況や治療経過、本人の生活環境や後遺障害等級など様々な事情から過失割合や損害額を検討して示談案が妥当かどうかを判断し、増額の可能性がどの程度あるかアドバイスをします。
相談者としては、弁護士からのアドバイスを受け、保険会社からの提案で示談をするか、弁護士に委任して増額を求めるかを判断することになります。
相談はお早めに
このように人身事故で弁護士に相談に行くタイミングは様々であり、適切なタイミングも人それぞれですが、早めに相談に行くことで対応に迷うことは格段に少なくなりますので、一般論として言えば早めの相談であればあるほど良いと考えます。
交通事故については弁護士費用特約が付いていることも多く、この場合には相談料はかかりませんし、当事務所をはじめとして無料相談を実施している法律事務所もありますので、ぜひお早目の相談をご検討ください。
弁護士 平本丈之亮