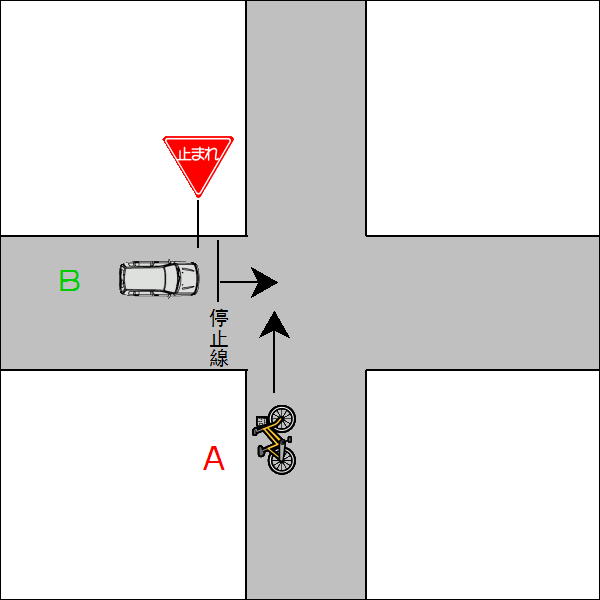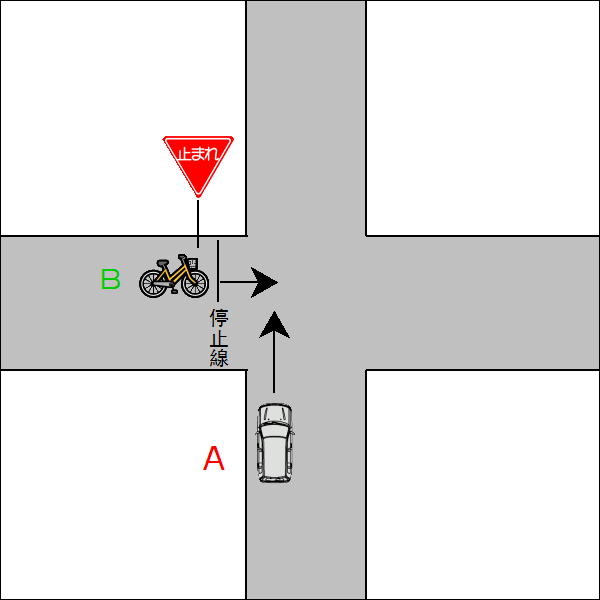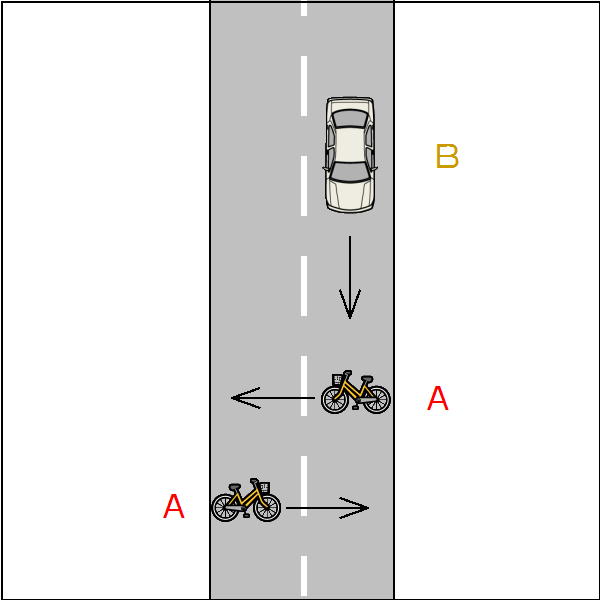交通事故で不幸にも受傷し、後遺障害が残った場合、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益の請求をすることになります。
通常、後遺障害事案では、一定期間の治療後、これ以上は治療しても効果があがらないという段階(症状固定)になってから損害額の計算をして示談交渉や裁判手続を行うことになります。
もっとも、稀なケースとして、事故後、被害者が治療を継続している最中に、肺炎などの別の病気や自死によって死亡してしまうことがあり、このような場合、相手方の保険会社から、後遺障害が確定していなかった以上、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益は支払えない、という対応をされることがあります。
今回は、このようなケースにおいて、本来であれば後遺障害が残っていたはずであるとして後遺障害に起因する慰謝料や逸失利益の請求はできるのか、という点についてお話しします。
後遺障害が残ることがはっきりしているようなケースのときは請求できる可能性がある
この点については否定例と肯定例の裁判例がありますが、死亡しなかったとしても後遺障害が残存した蓋然性が認められる場合には、残存したであろう後遺障害に基づく損害賠償請求ができる可能性があります。
肯定例
「前記のとおり、本件事故とAの死亡との間に相当因果関係は認められないが、仮にAが自殺をしなかったとすれば、後記のとおり、Aには後遺障害が残存した蓋然性が高かったと認められる。 →被害者の治療経過をもとに、被害者には13級相当の下肢短縮障害と12級相当の右股関節機能障害の併合11級の後遺障害が残存した蓋然性があるとした上で、被害者が症状固定前に死亡したことから障害が改善した可能性もあるとして、11級本来の労働能力喪失率20%から3%を減じた17%の労働能力喪失率を認め、これを前提に後遺障害逸失利益と後遺障害慰謝料を肯定した。
そのような場合は、残存する蓋然性が高いと認められる後遺障害を負ったものとして損害賠償請求権が成立するというべきである。」
「亡○は、本件事故により、脳挫傷等の重度の傷害を負い、遷延性意識障害の状態に陥り、ベッド上で寝たきりの生活となったことが認められる。被告は、亡○の症状は改善傾向にあったと主張し、確かに、△病院に転院した平成○年○月○日頃には、亡○は開眼し、声掛けに反応を示すこともあったが(乙3)、上記各証拠によれば、同時点でも意識は混濁で、体は一切動かせず、会話もできない状態のままであったこと、全身の骨折について外科的整復は行わず保存的加療となったまま、療養目的で入院していたこと、栄養補給は経鼻栄養補給で、自力排泄もできず、医師からは回復の見込みはないと告げられていたことが認められるのであって、亡○の本件事故後の状態は、後遺障害別等級表1級1号「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」に相当し、その状態で死亡に至ったものと認められる。 →後遺障害慰謝料を肯定(事故当時70歳を超える高齢者で生活保護受給者であったためか、逸失利益の請求はなし)。
とすると、亡○について、上記等級に対応する後遺障害慰謝料を認めるのが相当である。」
「亡○は、本件事故により脳挫傷等の重度の傷害を負い、遷延性意識障害の状態に陥り、ベッド上で寝たきりの生活となり、平成○年○月○日頃には、開眼し、声掛けに反応を示すこともあったが、その時点でも意識は混濁で、体は一切動かせず、会話もできない状態のままであり、全身の骨折についても保存的加療となったまま、療養目的で入院し、栄養補給は経鼻栄養補給で、自力排泄もできず、後遺障害別等級表1級1号「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」に相当し、遅くとも死亡までには症状固定したと認めるのが相当であることは、前記1説示のとおりである。亡○の後遺障害診断書(甲4)の症状固定日が空欄であることは、上記認定の妨げにはならない。」
否定例
「ところで、被害者が症状固定前に後発の事故により死亡した場合、先行事故による後遺障害の症状固定を前提とする損害の発生を認めることができるかであるが、先行事故による障害の治療中はそれによる後遺障害の有無、程度は不明であるし(殊に他覚的所見を伴わない「神経症状」については、死亡しなければ治療の継続により先行事故に基づく後遺障害が残存しなくなる可能性も否定できない。)、死亡時を症状固定時期とみなすことも著しい擬制を前提とすることになり相当とはいえない。」 「そうすると、・・・本件事故による上記障害の症状固定を前提とする逸失利益及び後遺障害慰謝料の請求はできないというほかない。」 →被害者は頸椎捻挫及び腰椎捻挫により両下肢の神経症状が残り歩行さえ困難となったとして、被害者の死亡時に症状が固定し、後遺障害等級9級10号に該当する後遺障害が残存したと主張したが、上記理由により後遺障害の主張は排斥。
以上のとおり、治療中に事故とは無関係の理由によって被害者がお亡くなりになった場合に、そのまま治療を継続していれば残存していたであろう後遺障害に基づく損害の請求については、肯定例と否定例が存在します。
もっとも、否定例をみても、先行事故による怪我の治療中は後遺障害の有無、程度が不明であることや、怪我の内容が他覚的所見を伴わない「神経症状」であったことが大きな理由になったものと思われるため、肯定例のように治療中の段階で既に後遺障害が残存する蓋然性が高く、その程度についてもある程度見通しがつくケースであれば、残存する蓋然性のある後遺障害等級を前提に後遺障害慰謝料や逸失利益の請求が認められる可能性があると思われます(要するに後遺障害が残ったであろうことを立証できるかどうかの問題)。
確かに、頸椎捻挫のように、レントゲンやMRIでは所見が認められづらい傷害だと、将来、本当に後遺障害が残存するかどうか不明な場合が多いと思われますが、肯定例のように元々の怪我の程度が重かったり、治療経過からある程度残存しそうな後遺障害が予想できる段階にまで至っていれば、症状固定前になくなった場合でも後遺障害に起因する損害を請求できる可能性はあると思いますので、そのようなケースについては弁護士へご相談いただくことをお勧めします。
弁護士 平本丈之亮